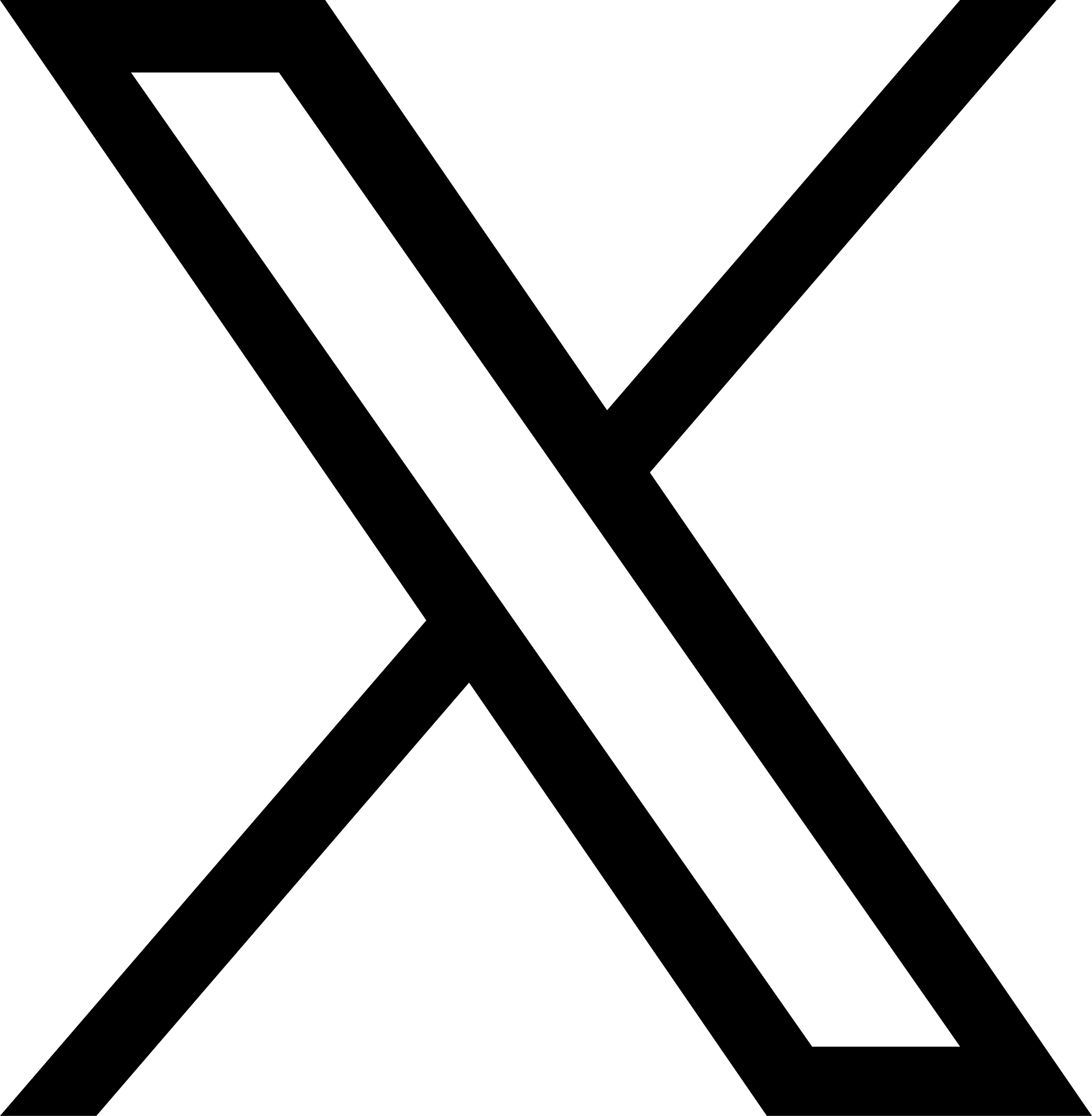豊臣兄弟とお茶
2026年の大河ドラマが発表され、豊臣秀吉とその弟の豊臣秀長(とよとみ ひでなが)の二人が主人公の物語なのだそう。
秀長は、豊臣秀吉の右腕として活躍した人物で、「もし秀長が長生きすれば、豊臣政権は長く存続したはず」と言われている程のキーマンだとされているのです。
豊臣秀吉とお茶の関係については以前のブログでも何度か触れてきましたが、実は弟・秀長も日本のお茶の歴史に大きな影響を与えた人物だったのです。
今回はそんな次の大河ドラマの主人公、豊臣兄弟とお茶についてわかりやすくお話ししたいと思います。
秀吉の実の弟
そもそも豊臣秀吉とは、戦国時代の終わりに日本をほぼ統一した武将で、農民の身分から天下人にまで上りつめたことで知られています。
織田信長に仕えて頭角を現し、その死後に後継者として勢力をまとめ上げました。政治や経済の仕組みを整え、平和な時代へと移る土台を作った人物です。
今回の主人公である豊臣秀長は、そんな豊臣秀吉の実の弟であり、「日本史上最も出世した」と言われている秀吉の補佐官として活躍しました。
豊臣秀吉が農家の出身であったことでも分かるように、彼もまた農民でしたが、秀吉が信長に抜擢されると信頼できる部下が欲しい秀吉に取り立てられ武士に「転職」したのでした。
しかし彼は「ただ秀吉の弟だったから」出世したわけではありません。
秀長は、秀吉の右腕として政務・軍事の双方で高く評価され、穏やかで誠実な性格から家臣や諸大名の信頼を集めたと言われています。
秀吉が急速に勢力を拡大できた背景には、秀長が内政や外交を安定させ、各地の大名との関係調整を丁寧に行ったことが大きく影響していたとされているのです。
特に、秀吉に任されて現在の奈良県の統治を任されるのですが、そこでは当時様々な宗教勢力が存在したにも関わらず、彼が統治する間には大きな争いが無かったとされています。
また、秀吉の決定に異を唱える事のできる数少ない人物であったとされており、多くの家臣から秀吉への取り次ぎ役として頼りにされていたと言われています。
秀吉の出世の陰には秀長の活躍があったのです。
そんな二人が「日本一の出世」を果たすために、「お茶」は必要不可欠でした。

千成瓢箪:豊臣秀吉が戦で勝利するごとに瓢箪の数を増やしていったという逸話に由来し、縁起物とされた秀吉の馬印(戦の時の目印)。大阪府の府章のモチーフにもなっている。
秀吉とお茶
そもそも秀吉の主君であった織田信長は茶の湯を権力の象徴として巧みに政治利用した最初の戦国武将といわれます。
それまで茶は一部の文化人の嗜みでしたが、信長は名物茶器を家臣への褒美や地位の象徴として与えていました。茶器の価値を金銀以上に扱うことで、それを所有することが武将としての名誉と権威を意味するように仕組んだのです。また、信長自身も茶会を通じて家臣や有力者を統制し、自らの教養と統率力を印象づけました。
彼の時代、茶の湯は単なる趣味を超えて、権力の道具として確立されたのです。
そんな信長に学んだ秀吉は、信長同様、戦で活躍した家臣に名物茶器を贈っていました。
さらには千利休を茶頭に抜擢し、茶会を通じて武将たちとの結束を強め、また自らの教養や格式を示したのでした。
以前のブログでも紹介したのですが、彼が茶の湯を天下人としての威信を示す場として最大限に活用した例として、「北野大茶会」があります。これは京都の北野天満宮で催され、身分や立場を問わず誰でも参加できる前代未聞の大規模な催しでした。
そこで集まった人々に秀吉は自らお茶を点てたと言われています。
秀長とお茶
一方、弟の秀長もお茶を人心掌握に活用していたとされています。
秀吉から客人の接待を任される事が多かったとされる秀長は、自らお茶を点ててふるまったり、お酒を注いで回る様な人物であったそうです。
博多の豪商・神屋宗湛の日記に、秀長が茶を点て、客をもてなした記録があります。宗湛は千利休や秀吉とも交流があり、そこに秀長も登場することからも、彼が茶の湯の作法に通じ、自ら客をもてなしたことがうかがえます。
秀長は奈良を拠点とした頃、堺の茶人や商人たちとも交流を持ち、自邸で茶会を催したとされています。特に、穏やかで誠実な性格から、彼の茶席は「豪華さよりも和やかさが際立っていた」と伝えられています。
ちなみに兄・秀吉はそんな秀長とは対照的に、豪華で派手な茶会を好んだ人物として有名です。
「黄金の茶室」に代表される様に、黄金好きの秀吉は、茶室まで豪華絢爛にしてしまうのです。
これが秀吉と彼が重用した千利休との不和が生まれた原因なのではないかともされています。
千利休の教えるお茶は、質素で精神性を大切にした「わび茶」が特徴で、茶室も簡素で小さく、素材や空間の取り合わせ、茶道具の趣向などを通して、心を落ち着け、精神の統一や一期一会の精神を大切にしました。

豊国神社:豊臣兄弟を祀る神社。大阪城内にあり、現在では「出世開運の神様」とされている。
秀長のいない豊臣家は
豪華絢爛な豊臣家の天下は盤石な様に見えたのですが、秀長が病に伏せると暗雲が立ち込めます。
秀吉が後北条氏を倒し、天下統一を達成した直後の1591年2月15日に秀長は病気で亡くなったとされています。
彼の死により秀吉の暴走を止める人がいなくなってしまったのでしょうか。直後の同年2月28日に秀吉はそれまで信頼し茶頭を任せていた千利休を切腹させてしまいます。
秀吉の暴走は続きます。
1592年に、秀吉は朝鮮出兵を行います。
これは朝鮮半島だけにとどまらず、明(当時の中国)まで征服しようという侵略戦争でした。ここから秀吉が亡くなる1598年までの間、戦いが続くことになるのです。
話はこれで終わりません。中々子供ができなかった秀吉に待望の跡取り息子が生まれた時、それまで秀吉の後継者とされていた秀吉の甥・豊臣秀次(ひでつぐ)に謀反の疑いをかけて、なんと粛清してしまうのです。
しかも秀次本人だけでなく、秀次の家族・一族・側近も大量に処刑するという徹底ぶり。
秀次は秀長の病気が発覚した際、健康祈願をしたという記録もあり、秀長を慕っていたことが分かっています。
もし、秀長がいたら、秀吉のこの暴挙を間違いなく止めようとしたことでしょう。
秀吉が亡くなった後、徳川家康に勝つことはできず、豊臣家は滅亡してしまいます。
これが「もし秀長が長生きすれば、豊臣政権は長く存続したはず」と言われる所以なのです。

秀長と遠州流
秀長が後世に与えたお茶の歴史への影響は他にもありました。
秀長の居城、奈良県の大和郡山城で、現代にまで繋がる出会いがありました。
秀長の家臣の一人に小堀遠州(こぼり えんしゅう)という人物がいたのですが、彼は後に武家茶道の一大流派・遠州流の開祖とされる茶人になるのです。
彼が秀長に仕える中で、大和郡山城を訪れた千利休や山上宗二といった一流の茶人と出会うことがきっかけとなり、茶道の世界に入っていくことになったと言われています。
やがて秀長の没後、遠州は秀吉・秀頼・徳川家康らに仕える立場に変わりますが、若き日に秀長のもとで培った教養と人間関係が、後の「遠州流」を形づくる基盤となったのかもしれません。
豊臣兄弟とお茶
このように、豊臣秀吉・秀長の兄弟は日本のお茶の歴史にも大きな影響を与えたのでした。
そんな豊臣兄弟は果たしてどのように描かれるのでしょうか。
いまからドラマが楽しみです。