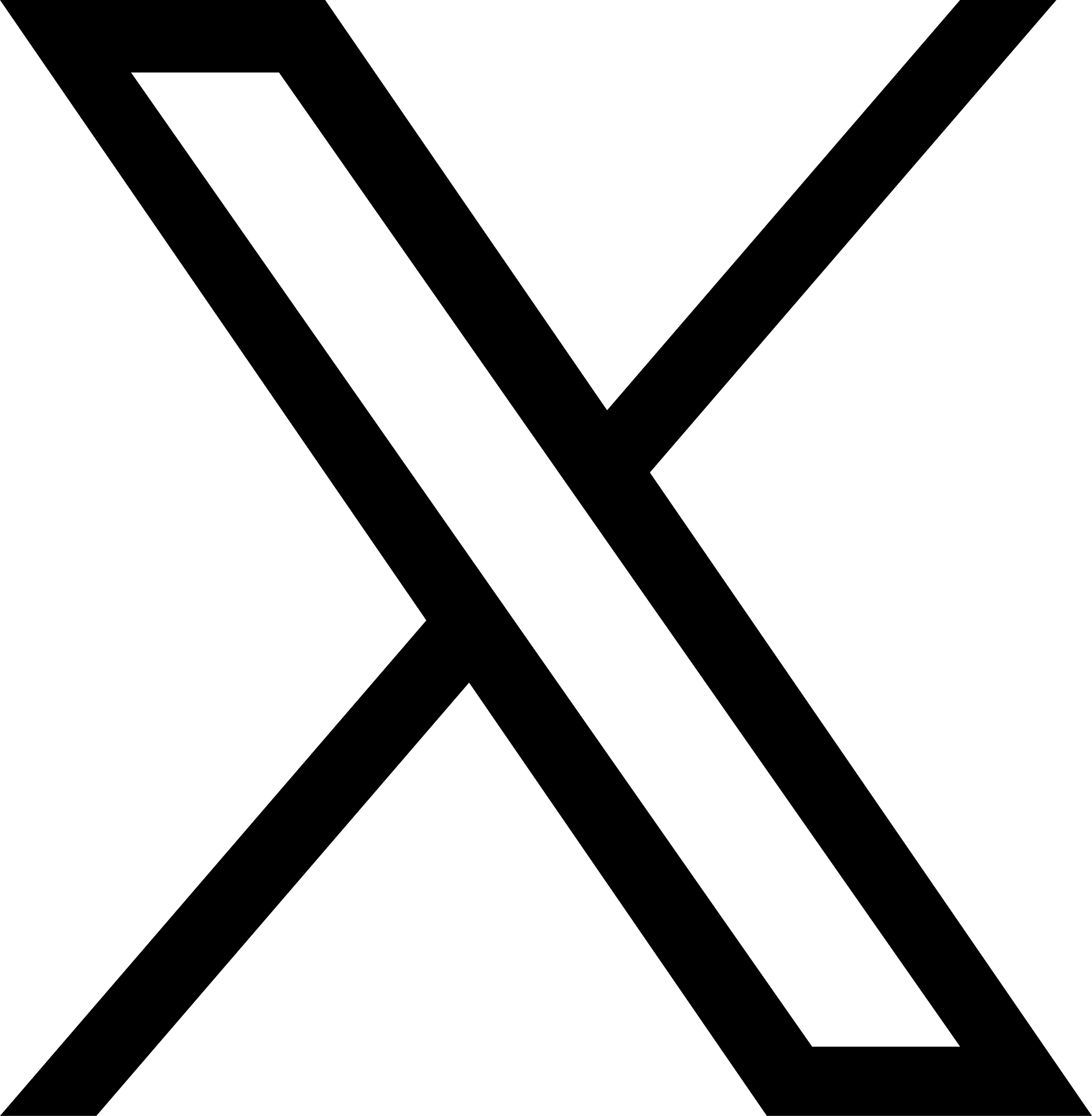10月31日は日本茶の日?
10月31日は何の日でしょうか。そう、ハロウィンですよね?ですが調べてみると、10月31日は「日本茶の日」でもあるそうなのです。皆さんご存知でしたでしょうか?
なんでもそれは、「栄西が中国(宋)からお茶の茶種と製法を日本に持ち帰った日」にちなんだものなのだそう。
これは多くのブログで説明されている「日本茶の日」が10月31日とされている理由なのですが、歴史好きな筆者は「?」となりました。
なぜかというと、栄西が活躍する時代は鎌倉時代ごろ。つまり800年以上前のことになります。
なぜ日付までわかったのでしょうか…?気になったので調べてみました。
10月1日も「日本茶の日」!?
調べて見ると、10月1日も「日本茶の日」として制定されているそうです。
つまり10月には1日と31日で2回、「日本茶の日」が存在するということに!?
10月1日の「日本茶の日」は公的な登録(日本記念日協会の認定)があり、伊藤園が2002年に登録したものなのだそう。
一方10月31日が「日本茶の日」となっているのは制定者不明。
つまり、誰が10月31日を「日本茶の日」としたかはっきりしていないのだそう。
日本茶の日について図書館で聞いてみた
筆者の地元の図書館で調べてみたのですが、10月31日に栄西がお茶の茶種と製法を日本に持ち帰ったという根拠になる資料は見つかりませんでした。
『茶の湯といけばなの歴史―日本の生活文化―』という本には以下の様な記載があるのだそうです。
「栄西が日本にもたらしたのは茶の種子であったか茶樹であったかあるいは第一回目の入宋(仁安三年 1168年)か二回目の入宋(文治三年 1187年)か、判然としない。最近の考え方では、種でも茶樹でもなかったという説が有力である。というのは栄西自身が『喫茶養生記』のなかでそのことに触れていないし、むしろ茶樹は日本に古来あったが利用法を知らなかったと記しているからである。したがって栄西がもたらしたのは、茶の製法、飲み方などの情報であったと見てよいだろう。」
つまり、栄西はお茶そのものを持ち帰ったのが2回の中国への渡航のどちらのことであったかも定かではなく、もしかしたらお茶そのものを持ち帰ったのではなくお茶の利用法を持ち帰ったのではないかという説です。その日付についても触れられていませんでした。
また、『茶の文化史』という本には「茶を伝えたのは二度目の帰宋の時とされ、持ち帰った茶種を平戸島の葦浦に植えた」と記載があるのですが、日付については情報がありませんでした。
ほかにも栄西の帰国について記載のある本がいくつかあったのですが、どれもその日付については見つける事ができませんでした。

画像は天正15年(1587)10月1日に「北野大茶湯」が開催された京都・北野天満宮
一方「10月1日の日本茶」は…
しかし、一方で、10月1日の日本茶の日については、その根拠となる歴史的な情報が多数出てきました。天正15年(1587)10月1日、豊臣秀吉が京都・北野天満宮にて大茶会「北野大茶湯」を催したことが由来で、身分にこだわらず広く参加を呼び掛け、建てられた茶屋は800あるいは1500とも言われているとても大規模な茶会だったのだそうです。これが日本のお茶文化を大衆に広めるきっかけになったとして、10月1日を「日本茶の日」としたのだそうで、これを裏付ける資料が多数存在しました。

栄西が京都最古の禅寺として創建した臨済宗建仁寺派の大本山建仁寺
栄西がお茶を広めたのは間違いないのですが…
以前のブログでも書いた通り、栄西が中国に学びお茶を広めたのは間違いの無い事実です。栄西は「喫茶養生記」という本を書き、お茶の健康効果を日本中に広めました。その功績は間違いないのですが、それを記念する「日本茶の日」が10月31日となった理由について突き止めることはできませんでした…
ハロウィンの裏で、謎が謎を呼ぶ「日本茶の日」が存在しました。
この謎について引き続き調べていきたいと思います。