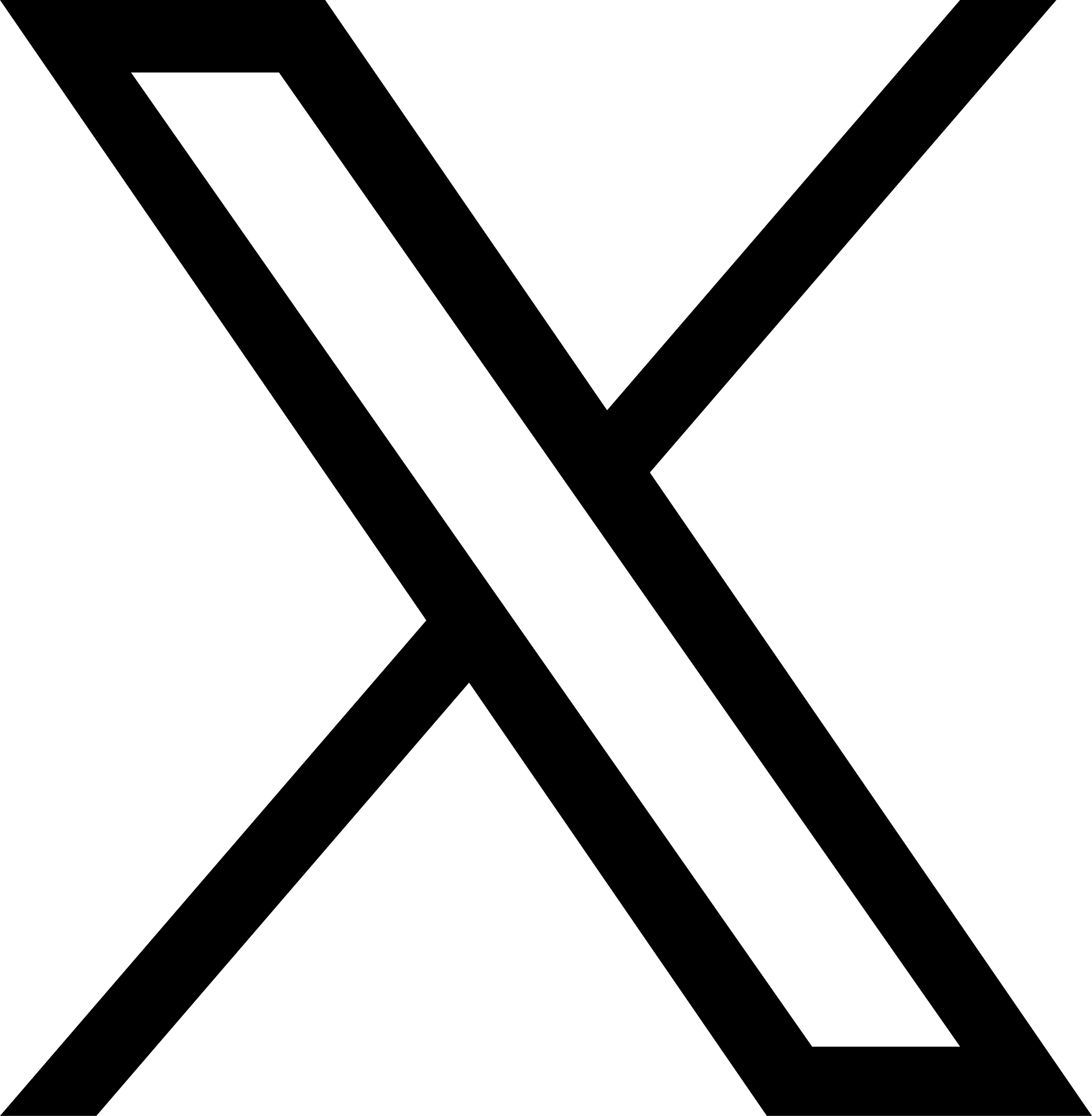石鎚黒茶と屋久島茶 茶畑を巡って
先日、私は、愛媛県の「石鎚黒茶」と鹿児島県の「屋久島」を訪ね、お茶づくりの現場を見学してきました。どちらの地域も、それぞれに独自の気候と文化を背景にした個性豊かなお茶を育んでおり、現地でしか感じられない空気や人の想いに触れることができました。
今回は、その様子をご紹介させていただきます。
石鎚黒茶

石鎚黒茶は、日本でも珍しい発酵茶の一種です。
収穫した茶葉を蒸し、糸状菌による一次発酵のあと、茶葉を揉み、密閉した容器で乳酸菌による二次発酵を行い、天日干しでしっかりと乾燥をさせるという手間のかかる製法。
1899では、数年前より店舗で提供させていただいており、また1899スタッフが現地視察と共に、刈り取りや製造体験にも参加いたしました。
今年も9月1日から11月30日までの期間限定で「ほうじ茶・番茶フェア」と題して、石鎚黒茶を含む秋の季節にピッタリのほうじ茶と番茶をご用意しています。季節の味覚たっぷりと盛り込んだスイーツもご用意しておりますので、是非お越しください。

私は今回初めてお邪魔し、改めてお茶が出来上がるまでの苦労や現地の方々の情熱を感じました。
まず刈り取り。
これまで何度か茶畑には足を運びましたが、今までの茶摘みとは全く別物でした。
茶葉を摘むというものではなく「伐採」。
しかも急斜面で刈込バサミを使います。
年配の方も多く、これはなかなかの重労働。
この日は、明け方6時前から行い、8時頃まで刈り取りをしました。
ボランティアの方も多く、石鎚黒茶を愛している人たちによって支えられていることを感じた時間になりました。

その後、製茶する現場へ移動。
まずは刈り取った枝葉を、この後の煮る工程が行いやすいようにカットしていきます。
これもなかなかの重労働。
万能バサミで約4時間ほどかけて、刈り取った枝葉を剪定していきます。
これは人手が重要です。
この後の詳細は、以前の別ブログで細かくご紹介していますが、
機械を使っているわけでもなく、全て人の手で行っており、伝統的な製法を守り続けていくことの苦労と素晴らしさの両面を感じました。
当日は、西条市の高橋市長も訪問され、現地を見学されていました。
地域の人々と、清らかな水と山の空気がこの茶を育むのだと実感しました。
作業中にいただいた冷たい石鎚黒茶は、ほんのり酸味を帯び、柔らかな香りが広がります。
まるで熟成されたお茶が語りかけるような、深い余韻が印象的。
当日は非常に暑かったため、冷たい石鎚黒茶が身体を癒してくれました。
屋久島のお茶の魅力

次に訪れた屋久島は、世界自然遺産にも登録された豊かな自然環境が広がる島。年間降水量は日本屈指で、その恵みを受けた茶畑は、まるで緑の絨毯のようでした。
1899では、今年の新茶フェアの際、屋久島のお茶を提供させていただきました。
お茶の美味しい味わいはもちろんのこと、「屋久島にお茶があるなんて知らなかった」と多くのお客様からお声をいただき、 東京でお茶の店舗を行っていることの意義を感じた次第です。

今回お邪魔したのは、店舗でもそのお茶を提供させていただいた八万寿茶園(はちまんじゅちゃえん)。
1980年代に、屋久島生まれの同級生三人が立ち上げた茶園で、2001年には茶工場を含む茶園全域にわたって有機JAS認定を取得した地域に根差した茶園です。
屋久島のお茶は、新芽の柔らかさと瑞々しい香りが特徴。
生産者の渡邉桂太さんは「当園は肥料を使わず放棄栽培を中心にしています。世界自然遺産の地で、自然のサイクルによって調和が保たれた環境でお茶を栽培しています」と教えてくれました。一般的に有機栽培のお茶は、全体の約4%とのことですが、屋久島では、有機栽培の比率が約30%と高いのも特徴なのだそう。

屋久島には、15の茶園があり、それぞれお茶の各工程を担っており、役割やタイプが異なるとのこと。屋久島では、タンカンなどの果樹の生産量が注目されるのですが、農作物の売上高では、実はお茶が一位だそうで、このことをもっと前に押し出していきたいと渡邉さんは話していました。屋久島は、面積503平方キロメートルと、日本の島の中で5番目に大きい島であり、綺麗な六角形をしていて、中心にある山々が常に視界に入り、その自然の偉大さ・存在感を感じる町です。今回は、渡邉さんをはじめ、町役場の方々、また屋久島の魅力を発信されている活動をしている方など、多くの方々にお話を伺いましたが、皆さんが共通しているのは、屋久島憲章という屋久島に係る全ての人が守るべき原則をベースに、この自然を大切に守っていこうという志が高いこと、またその地からの恩恵に感謝し生活していることでした。
現地でしか得られない学び
どちらの産地でも共通して感じたのは、生産者の方々の「その地に誇りを持ち、引き継がれてきたお茶の歴史を大切に守りながら、お茶と向き合っている」という強い想い・姿勢です。石鎚黒茶の長い発酵工程も、屋久島茶の島のしぜんと共存する姿勢も、すべては飲む人の笑顔を思い浮かべながら行われていました。
お茶は、ただの商品ではなく、土地の風土や人の心を映すもの。現地に足を運ぶことで、そうした背景を肌で感じられたことは、大きな収穫でした。
今後は、生産者の方々の思いを直接お届けする機会も作っていきたいと考えています。